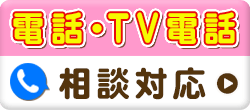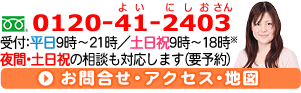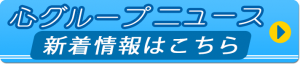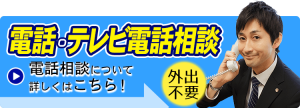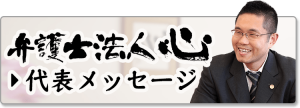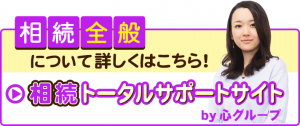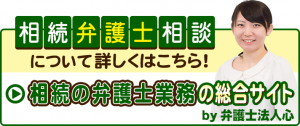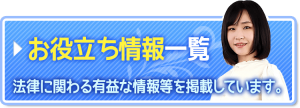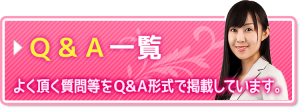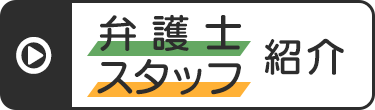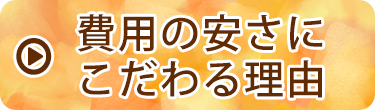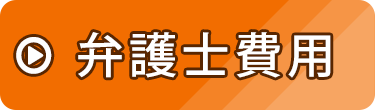相続放棄の手続きに関するQ&A
- Q相続放棄は口頭でできますか?
- Q相続放棄の手続きはいつまでに行う必要がありますか?
- Q相続放棄の手続きはどのような流れで進みますか?
- Q相続放棄の手続きではどのような点に注意すべきですか?
- Q相続放棄の手続きにはいくらかかりますか?
Q相続放棄は口頭でできますか?
A
相続放棄は、口頭ではできないので注意が必要です。
相続放棄をするためには、法律で定められた期限内に、管轄の家庭裁判所に対して相続放棄申述書や戸籍謄本類などの必要書類を提出する必要があります。
Q相続放棄の手続きはいつまでに行う必要がありますか?
A
相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」行う必要があります。
この期間内に、相続放棄に必要な書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
一般的には、被相続人がお亡くなりになられた日から3か月以内に相続放棄をすれば問題ありません。
長年被相続人が音信不通であったという場合において、被相続人の債権者からの書面が届き、例えば1年前に被相続人がお亡くなりになっていたことを知ったというような場合には、債権者からの書面を受け取った日から3か月以内に相続放棄の手続きをする必要があります。
Q相続放棄の手続きはどのような流れで進みますか?
A
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に、相続放棄申述書と戸籍謄本類などの必要書類を提出すること(「申述」といいます)で開始されます。
管轄の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記載されている住所)を管轄する家庭裁判所となります。
書類を提出すると、家庭裁判所による審査が開始されます。
相続放棄の申述に至った事情や、裁判所の方針によっては、家庭裁判所から申述人に対して質問状が送付されることもあります。
質問状に回答を記載して家庭裁判所に返送した後、相続放棄申述書や質問状への回答などに問題がないと判断されたら、相続放棄申述受理通知書が発行されて手続きは終了します。
あまり多くはありませんが、法定単純承認事由が存在する可能性があるなど、複雑な事情がある場合には、質問状の送付のほか、家庭裁判所での審問が行われることもあります。
Q相続放棄の手続きではどのような点に注意すべきですか?
A
まず、最も大切なのは、期限までに相続放棄の申述を行うことです。
相続放棄の期限はとても短く、期限を過ぎてしまうと取り返しがつかなくなってしまうので注意が必要です。
財産の調査に時間が必要で、相続放棄の期限までに調査を終えられない可能性がある場合には、相続放棄の期限を延長する手続きを行いましょう。
次に、相続放棄の申述を行った後に家庭裁判所から送付されてくる質問状に回答する際には、相続放棄申述書に記載した内容と矛盾がないようにしましょう。
家庭裁判所が質問状を送付する目的のひとつは、なりすましによる相続放棄でないかを確認することであると考えられます。
もし相続放棄申述書に書いてある内容と、質問状の回答内容が違っていると、なりすましによる相続放棄なのではないかと思われてしまう可能性があります。
Q相続放棄の手続きにはいくらかかりますか?
A
相続放棄をするためにかかる費用は、主に戸籍謄本類を収集する費用、相続放棄申述の際に家庭裁判所に納める収入印紙代と予納郵券代、家庭裁判所までの交通費または郵送費です。
戸籍謄本類の収集には、一般的には数千円程度です。
相続放棄申述の際に家庭裁判所に納める収入印紙代は800円、予納郵券代は数百円程度です。
管轄の家庭裁判所が遠方である場合、交通費は高額になる可能性があります。
郵送で相続放棄の申述をする場合、郵送費は数百円程度となります。
相続放棄を弁護士に依頼する場合、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は事案の難易度によってある程度異なりますが、一般的には数万~十数万円程度となります。